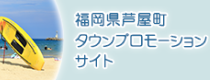本文
後期高齢者医療制度
制度の概要
これまで国民健康保険や被用者保険(健康保険や共済保険など)で医療を受けていた人は、75歳になると「後期高齢者医療制度」の被保険者になり、国民健康保険や被用者保険の資格は喪失します(65歳以上75歳未満で一定の障がいについて広域連合の認定を受けた方も同様です)。
これは、老人の医療費が増大するなか、現役世代と高齢者世代の負担と給付を明確化し、75歳以上の高齢者の心身の特性や生活実態等を踏まえ、高齢化社会に対応する公平で分かりやすい制度として創設されたものです。
自己負担割合と主な給付
医療機関等での自己負担割合は、所得により1割~3割となります。
後期高齢者医療制度で受けられる主な給付は、次のとおりとなります。
- 療養の給付費(入院及び外来で診療を受けた時の治療費など)
- 入院時食事療養費(入院した時の食事代)
- 入院時生活療養費(療養病床入院時の食事・居住費)
- 高額療養費(同一月内に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた時の給付費)
- 高額介護合算療養費(8月から翌年7月までの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額が一定の限度額を超えた時の給付費)
- 療養費(補装具等の購入費など)
- その他の給付(訪問看護療養費、移送費、葬祭費)
保険料の決定と納付
医療費の総額から、病院などで支払う一部負担金を除いた費用(医療給付費)のうち約5割を公費(税金)で、約4割を後期高齢者支援金(現役世代の保険料)で負担し、残りの1割を後期高齢者の保険料で負担します。
後期高齢者医療制度では、介護保険と同様に、被保険者一人ひとりに対して保険料を賦課し徴収します。保険料は被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計金額になります。
また、所得の少ない世帯に属する人は、世帯の所得に応じて「被保険者均等割額」が軽減される措置があります。 保険料の納付については、原則として年金から天引きされます。年金の額によって、年金から天引きされる「特別徴収」と納付書などで納める「普通徴収」により納めることになります。
詳しくは、福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。